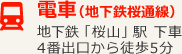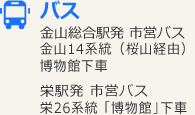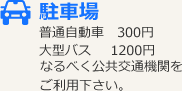-
野良着
野良着

写真1‐1 野良着のシャツ

写真1‐2 野良着のシャツ(部分)
このシャツは、野良着として守山区中志段味で収集された。昭和期に使われたということ以外、どのような作業のときに誰がどう着ていたのか、残念ながら当人からの聞き書きは記録に残っていない。
シャツの野良着については、『仕事着―東日本編』(昭和59年調査)の愛知県の調査結果によれば、男性の仕事着として明治中頃から詰襟のシャツが入ってきて、県下全域に普及していったという。また、男女とも仕事着が和装から洋装へと移り変わるのは、第二次世界大戦を境とする時期と記述している。また、『新修名古屋市史第九巻民俗編』(平成5年~11年調査)には、明治末から大正中頃まではハンテン・モモヒキの着用が普通であったが、調査で聞き書きした古老のころにはシャツとズボンが多くなってきたと述べている。このことから、このシャツを着ていた時期は和装から洋装へと移り変わるころだったといえる。
このシャツを見ていくと、タグが付いていることから既製品であることがわかる。裾部分が長いため、腰をしっかり覆うことができて野良仕事には最適だっただろう。ボタンホールのほつれや色あせから、何度も着古されたものと見て取れる。注目すべきは、袖。袖口を見ると、通常シャツに見られるカフス部分がない。シャツの仕立てはミシンで縫われているのに対して、袖口だけは黒の木綿糸でくけ縫いされている。おそらく、既製品の袖では野良仕事に長すぎて不都合だったため、切って仕立て直したのであろう。
農業や漁業、林業などに従事する際に着る仕事着は、作業のしやすさを重視した形状になっていて、袖の部分はそれがよく表われる。シャツといっしょにもらい受けたデンチという袖なしの半纏は寒いときに着用する綿入れだが、袖付け部分は大きく開いており、野良仕事で腕を前後左右に動かしても邪魔にならないようになっている〔写真2参照〕。

写真2 デンチ
着物の仕事着の場合、袖の形は筒袖や鉄砲袖など、袖口が狭い形になっている。やはり、作業のしやすさを重視した形だ。名古屋市周辺地域ではフワと呼ばれる女性の普段着の上っ張りがある。天白区に住む障子の張り替えなどを家業としている家の女性にその使用方法を聞いた〔写真3参照〕。上っ張りは、着物の上から羽織り、両衿の下部と脇についた紐を互い違いに結んで着る。女性はこれを着て、家業を手伝い、家事をしていたという。生地は木綿やウールで、自製したものと店で売られていたものとがあった。袖の形は袖口が小さく絞られた筒袖で、袖口にゴムが入っているものもある。自製のものは意図的に袖丈を少し短く作っている。色も汚れても目立たないように濃い色を着ていたという。

写真3 着物の上から羽織る上っ張りの様子
このフワと先のシャツの事例を合わせて考えると、和装から洋装へと仕事着が変化していくなかでも、袖部分には作業のしやすさを重視して短くするという共通の意識があることがわかる。
もう一つ洋装の仕事着の例を挙げよう。中川区下之一色で聞き書きした毛糸のセーターである。下之一色は昭和34年に漁業権を放棄するまで、漁業の町として栄えていた地域で、そこに生まれ育ち漁業に従事していた男性は、冬の寒い時期には首元を覆うタートルネック型のセーターを着たという。この地には、着物を何枚も合わせて刺し子にしたカワジュバンという着物の仕事着も残っているが、男性が漁業の仕事をしていた晩年には、洋装の仕事着も着用していた。タートルネックのセーターを男性はその形から「とっくり」と呼んだ。とっくりは男性の妻による手作りで、首を覆うため風が入りにくく暖かで、袖は七分袖に仕立てているため、作業に適しているという。聞き書きした当時、そのとっくりを身につけて見せて下さった。長年着用したために袖には少し穴が開いていたが、男性自身で繕っており、大切にしていることがうかがえた。
和装から洋装になり、既製品が使われるようになっていても、着物の仕事着に見られるような袖への配慮をみることができた。生活様式が変化していくなかで、服装は変化しても使い勝手の良さを重視した工夫は受け継がれているのである。
(佐野尚子)
※本資料は常設展示しておりません。あしからずご了承ください。
参考文献
・神奈川大学日本常民文化研究所編 『仕事着―東日本編』神奈川大学日本常民文化研究所調査報告第11集 平凡社 1986年
・新修名古屋市史編集委員会編『新修名古屋市史 第九巻民俗編』 名古屋市 2001年
・名古屋市博物館編『採録名古屋の衣生活 伝えたい記憶 残したい心』 名古屋市博物館 2017年