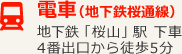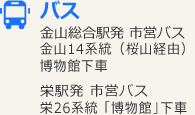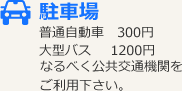-
金小札紅中萌黄糸縅腹巻
きんこざねべになかもえぎいとおどしはらまき
金小札紅中萌黄糸縅腹巻

甲冑の前側

甲冑の背中側(スリットはイセエビのようにも見える背板で覆われている)
尾張藩士の武具
今日では「腹巻(はらまき)」とよばれる室町時代に好まれた形式の甲冑である。皮革と鉄でつくられた「本小札(ほんこざね)」という小さな札を、漆でコートしてさらに金箔を貼り、紅色と萌葱色の絹糸で綴り合わせた精緻な造りで、背中側の着脱用のスリットをカバーする背板が付属している事も珍しく、かなり身分の高い武士が用いたと思われる高級品である。構成を説明すると、小札(こざね)を長側(なががわ・胴回り)は4段に並べ、立挙(たてあげ・胸部)に札2段分増している。胴から垂れ下がり腰回りを守る草摺(くさずり)は5段、肩を守る広袖(ひろそで)は7段で構成されている。紅色・萌葱色の糸で札を上下左右に繋ぎ、札の糸で隠された部分は生漆のまま、むき出しの部分は金箔が貼られている。各パーツ上部の鉄板でつくられた部分は下地に鮫皮を貼り、金箔を押している。胴の内側は漆塗りした革で包まれている。
この甲冑が伝来した尾張藩士中村家は、初代尾張藩主徳川義直の兄で、義直より前に尾張を治めた松平忠吉が武蔵国忍城主だったときに仕えた家である。甲冑の由緒については伝わっていないが祖先伝来の甲冑だとすれば、武蔵国時代の中村家の家格がうかがわれる。なお幕末の当主、中村修は勤王家として活躍し維新後は要職を歴任して初代名古屋市長も務めた。中村家では兜と籠手(こて)を添えて一具としていたが、制作年代がそれぞれ異なるため、当館では別資料として取り扱っている。
日本の甲冑は平安時代に誕生した「大鎧(おおよろい)」という形式が基本形となりつつ、時代や戦術の変化とともに何度かの変革期を迎えた。大鎧は胴体が四角い箱形をしており、草摺(くさずり)も前後左右の4枚である。右脇腹の部品「脇楯(わいだて)」を取り外して着脱するようになっている。正直少々歩きにくく、馬にまたがって移動し弓射で戦うことを前提にしている。これに対し腹巻はもともとは今日の剣道の胴のように胴体の前面だけにあてがう「腹当(はらあて)」という簡易な防具が前身で、室町時代に背面まで覆うように進化した物である。大鎧より体型にフィットさせやすく、重みも肩ではなく腰で受けるので活動が楽になった。草摺も7枚(背板の分も入れれば8枚)に割れて足捌きも軽快である。このほかに、腹巻に似るが、右脇腹に着脱用のスリットのある「胴丸(どうまる)」という形式もあり、これをもとに戦国時代には防御力と生産効率を上げた「当世具足(とうせいぐそく)」と呼ばれる多様な形式が考案された。安土桃山時代には実戦で使用されるのはほぼ当世具足のみとなり、それ以前の形式の甲冑は戦場から姿を消した。ただし、大鎧は最も格調の高い甲冑、名家の由緒を示す家宝と認識され、実戦で使用されていないにもかかわらず、江戸時代以降に描かれた合戦図屏風や武士の肖像画では大鎧を着用した姿が描かれている。また、江戸時代後期には(調度品としてだが)多くの復古調大鎧が制作された。それに対して、あくまでも実用品であった「腹巻」と「胴丸」は顧みられることがなかった。実は「腹巻」と「胴丸」という言葉は実際に使用されていた中世ではお互い逆の形式を指していたが、江戸時代後期の有職故実研究家に取り違えられてしまってそのまま定着し、今日の文化財指定名称でも逆さまのまま使われているのである(なので、本来はこの甲冑は胴丸と呼ぶべきかもしれない)。
そういう意味でも、室町時代の「腹巻」がこれほど状態良く整った姿で伝来していることはきわめて貴重な事例である。特に、臆病板(おくびょういた)ともいい、散逸しやすい部品である背板が付属していることは珍しい。
(山田伸彦)
室町時代後期 胴高28.4cm
※本資料は常設展示しておりません。あしからずご了承ください。