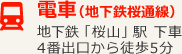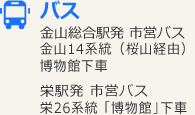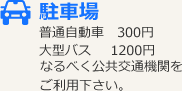-
丹羽嘉言 神洲奇観図―みずみずしい富士山の姿
丹羽嘉言筆 神洲奇観図―みずみずしい富士山の姿

悠々と裾野を広げる富士の姿。山肌を彩る藍色はとても瑞々しく、爽やかな美貌を我々に示す。本作は、江戸時代の中頃、名古屋の地で活躍した文人画家、丹羽嘉言(にわかげん、1742年~1786年)が描いた写生風の富士山図である。
丹羽嘉言について−尾張文人画の先駆者
嘉言の出自は不明な点が多いが、裕福な商家に生まれ、やがて武士の身分を得たと考えられる。生家に恵まれた嘉言は、上京する機会もあり、様々な学問や諸芸に親しんだようだ。画技はその内の一つであり、当時最新の動向であった文人画に関心を寄せた。文人画とは、文人(知識人)が自らの学識を糧に余技として描くという中国絵画の理想を尊重したもので、江戸時代の中期以降、漢学者を中心に受容された新しい絵画ジャンルであった。具体的な様式は中国製の絵手本を参考にするなど手探りであったが、嘉言はこの新しい芸術に魅了され、独自の画風を開拓していく。嘉言の作品は、儒学者や学問を嗜む富商など当地の知識人たちに愛された。当地において、嘉言が文人画の先駆者とされる所以である。それでは、文人画と本作のような富士山の絵にどのような関係があるのだろうか。
描かれた場所
まずは描き収める富士山や周辺の様子、表現の手法を詳しく見ていこう。本作では富士山を、画面向かって右方に寄せて、左方に伸びやかな稜線を配置する。右下には、起伏に富んだ愛鷹山(あしたかやま)を写し、宝永山(ほうえいざん)のこぶが有ると思われる個所は雲霞で隠したようだ。左方の麓には家屋の連なりや水景の広がりが確認でき、原宿(はらしゅく)や吉原宿(よしわらしゅく)といった宿場町に加え、浮島ヶ原(うきしまがはら)の池沼を描くと想定できよう(挿図1)。

挿図1 神洲奇観図 部分
主役の富士は、上部三割程に雪を頂き、麓の色鮮やかな彩色と併せて考えると、春から初夏までの季節を意識しているようだ。
富士山は古来より名所として歌に詠まれ、また絵画に描かれてきた。とは言え、多くの人々にとって現実の富士山の姿は馴染みが無く、山頂が三つに分かれた「山の字型」の富士山が象徴的な図像として定着する。併せて三保の松原を添えた作品も定番として多く描かれた。やがて江戸時代の中頃になると、現地の写生に基づく多様な富士図が現れた。それは、街道の往来が盛んになるに従い、人々の実景に対する関心が高まったことを背景としている。本作も、伝統的な富士山図の図像や構図とは異なり、写生を基礎とした作品であることが想像されるものである。
実際に、嘉言が富士山の写生を試みたことが文献資料から判明する。嘉言の詩文を集めた『謝庵遺稿』には、数日にわたって富士山の写生をおこなったことが記録されている(『謝庵遺稿』「題自画九首」)。本作は、その際の写生の成果を活かして仕上げた清新な江戸期の富士山図と位置付けられよう。
「実景」と「真景」の違い
ところでこの清新さは、気ままな写生を通じてもたらされたものではなく、ある理論を意識して意図的に生み出されたものであった。嘉言は、現物を観察することなく旧来の図様を描き継いだ富士山図に不満を持ち、写生を通じて「新意」に溢れた作品を描き、富士山の「真景」を描き尽くそうと努力したことが知られている(『謝庵遺稿』「書雪斎鳴門泄潮図後」)。ここで言う「真景」とは、中国の画論で用いられた用語であり、必ずしも現実の地勢を見たままに写し取った実景という意味ではない。ただし対象の「真」なる景を感得するために、実景に対峙することが重要視された。我が国では、中国の画論を信奉する文人画家を中心にこの「真景」論が受容された。嘉言もその一人であったが、「真景」の理解は一様ではなく、実景と同義に用いられる例もあった。
日本で「真景図」を制作した先駆者として、京都の文人画家、池大雅(1723年から1776年)が挙げられる。大雅は頻繁に旅に出て、その都度目にする実景を写生帳に描き留めた。しかし実際の「真景図」制作では、あくまでも中国の文人画家の構図や様式で描くことにこだわっている。大雅にとっての「真景」は、見たままの実景とは異なるものであった。大雅は日本の実景を、中国絵画の表現で描き改めることで「新意」を出し、「真景」に迫ろうとしたのである。果たして嘉言の場合はどうであろうか。
嘉言の「真景図」
大雅の複雑な「真景図」と比較すると、本図は実景をそのまま描き留めているように感じられる。とりわけ画面右下を占める愛鷹山の表現が注目されよう(挿図2)。水分を含んだ幅広の筆致から乾いた細切れの筆致まで、多様な筆づかいによって、山肌の凹凸を表現している。

挿図2 神洲奇観図 部分
これらの筆遣いは形式化されたものではなく、手探りで描き進められた印象を受ける。おそらく現地での写生図をもとに、実見した経験を思い出しながら描いたのであろう。全体に目を広げても、淡く柔らかな色調で統一されているため、写生図そのものを思わせる軽やかさにあふれている。「真景」を描くために嘉言が選択した手段は、実景に対峙した感動を素直に伝達することであった。
一方、一幅の作品として整理された表現も確認できる。主役となる富士山と前述の愛鷹山は、面的で伸びやかな筆致と線的で細やかな筆致とで描き分け、明瞭に対照されていることが分かる。奥行きの表現も、樹木の大小や濃淡を調整することで、前後が明らかに示される。実景を写生した経験を踏まえ、その感興を尊重しながら、美しく整理していると理解できる。
本図に年紀はなく、制作年代は不明である。ただし、同様に写生風の様式を採用する何点かの富士山図に明和七年(1770)の年紀があり、本作も同時期の作例と考えられる。嘉言は30代前半、未だ若い時期の作例であるが、写生を基盤とする清新な様式の完成形と位置付けられる作品である。本作のような嘉言の富士山図は、当地において画期的な作品として歓迎されたらしく、弟子の巣見来山(すみらいざん、1757年~1821年)をはじめ、後世の文人画家である中林竹洞(なかばやしちくとう、1776年~1853年)、山本梅逸(やまもとばいいつ、1783年~1856年)の模倣作も報告されている。嘉言の富士山図は、当地の文人画家による「真景図」の先駆的作例として、評価を受けたことが想像できよう。
(横尾 拓真)
※本資料は常設展示しておりません。あしからずご了承ください。
参考文献
吉田俊英「丹羽嘉言神洲奇観図・中林竹洞神洲奇観図」『國華』1032、1980年3月
吉田俊英「丹羽嘉言と尾張初期南画の状況」『名古屋市博物館研究紀要』4、1981年3月
清水孝之「丹羽嘉言における写生と写意」久保尋二 編著『芸術における伝統と変革』多賀出版株式会社、1983年12月