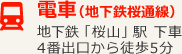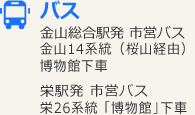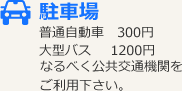-
月僊「仏涅槃図」
月僊「仏涅槃図」
縦が342cm、横が273cmにも及ぶ大画面。1点の絵画作品としては当館で最大の大きさを誇る涅槃図である。江戸時代の中ごろに活躍した名古屋生まれの画僧、月僊(1741~1809)が、天明六年(1786)に描いたものだ。今回は、ユニークな画風で人気を博した画家による個性あふれる涅槃図を紹介したい。

仏涅槃図
月僊について
月僊は、旧蛯屋町(現西区城西)の味噌商、丹家八左衛門(はんげはちざえもん・通称彦八)の家に生まれ、七歳で仏門に入り、浄土宗の僧となった。江戸や京都で修業するかたわら、桜井雪館(さくらいせっかん・1715~90)や円山応挙(まるやまおうきょ・1733~95)に絵を学んだ。安永三年(1774)には、伊勢山田の下中之地蔵(しもなかのじぞう)町(現伊勢市中之町)にある寂照寺(じゃくしょうじ)の住職となり、絵を売って蓄えた資を元手にその再興に努め、また貧民救済にも尽力したと伝えられる。ユニークな仙人の絵で人気を博したが、山水画や花鳥画、また本作のような仏画など幅広い主題を描いた。
養林寺伝来の涅槃図
涅槃図は、仏教の開祖である釈迦(しゃか)の肉体的な死の情景を描いた絵画で、概ね床に横たわる釈迦とその死を悼んで周囲を囲む人々が描かれる。釈迦の遺徳を追慕する法要、涅槃会(ねはんえ)の本尊として古来より数多くの涅槃図が制作されてきた。本作は、旧白川町(現中区栄)にあった養林寺(ようりんじ・戦後は昭和区西畑町に移転)に伝来し、林霊法(はやしれいほう・1906~2000)住職より寄贈を受けたものである。養林寺は、織田信長の重臣、林秀貞(はやしひでさだ・通勝(みちかつ)として広く知られる、?~1580)が、永禄五年(1562)父の菩提を弔う為に岐阜に建立したのが始まりとされ、その後清須を経て名古屋に移った。上級の藩士を檀家に持ち、郊外には新田を有するなど、城下では寺勢の盛んな寺で、月僊の生家である丹家(たんげ)家の菩提寺でもあった。その縁から、月僊に本作の制作依頼が寄せられたと思われる。安永九年(1780)、養林寺は火災によって伽藍のほとんどを焼失しており、本堂の再建に合わせて本作も制作されたと推測されている。
本作が制作された天明年間は、月僊の画業において画風が確立する寛政年間につながる時期であり、円山応挙の影響が窺える丁寧な仕上げの作品が多い時期である。本作もモティーフの一つ一つを緻密に仕上げて巨大な画面を埋めており、大変見応えのある涅槃図となっている。以下、本作の図様や表現に着目しながら、その特徴を見ていこう。
伝統の継承 涅槃図の形式について
本涅槃図の画面構成、釈迦の涅槃に集った諸衆の図様は、先行する作例を引き継いでいると思われる。涅槃会に欠かすことのできない涅槃図は、古来より描き継がれており、現存作例も応徳三年(1086)の銘を持つ高野山金剛峰寺(こんごうぶじ)本を最古例として数多い。日本に伝存する涅槃図の図様については、大きく二種類の形式に分けて整理されている。分かりやすい注目点の一つは、釈迦が横たわる宝床(ほうしょう)の向きであり、第一形式は向かって右側面が覗き、第二形式は向かって左側面が覗くといった特徴がある。第一形式は平安時代の作例に多く、鎌倉時代以降、第二形式の作例が中心となっていった。以上の条件を踏まえると、本涅槃図は第二形式に分類されることが理解できるだろう。さらに細部を見ていくと、第二形式のなかでも特定の作例の系譜に連なることが想定される。例えば、宝床の前方で横たわる弟子、阿難陀(あなんだ)に水をかける阿那律(あなりつ)(挿図1)、一際大きな身体の仁王(におう)(那羅延金剛(ならえんこんごう)・密迹金剛(みっしゃくこんごう))(挿図2)、釈迦に最期の布施(ふせ)を行った鍛冶屋の純陀(じゅんだ)(挿図3)など識別しやすい登場人物を手がかりにすると、近似する図様の涅槃図を見つけることができる。鎌倉時代の作例とされる滋賀県高島市安曇川(あどがわ)町、正法寺(しょうほうじ)本(重要文化財)、康永四年(1345)、南都絵所(なんとえどころ)の絵仏師(えぶっし)によって制作された東京、根津美術館本がそれである。この系統の図様は、名古屋市中区、乾徳寺(けんとくじ)本など近世名古屋城下の作例にも確認できる。月僊は、本涅槃図を制作するにあたり、粉本(ふんぽん・制作の参考となる摸写や草稿)などを通じて先行する涅槃図の図様を素直に受け継いだようである。もちろん、つりあいの取れた身体表現等は月僊の画技の高さを反映しているが、釈迦や会衆の基本的なポーズは先例に基づいている。

挿図1

挿図2

挿図3
新しい表現 清新な色使いと写生画風
一方、近世の涅槃図として目新しい要素は彩色と言えそうである。白い画面の清澄さを活かした色使いは、涅槃図の歴史の中でも異色と言えるだろう。例えば、釈迦を取り囲む八本の沙羅(さら)の樹、うしろを流れる跋提河(ばつだいが)、二月十五日の満月の夜空といった背景を見てみよう。一般的には、青や緑の濃い絵の具が塗られる部分であるが、本作では墨と淡い色彩を用いてあっさりと仕上げられている。そうすることで、釈迦や会衆の衣服、装身具に見る濃厚な彩色を目立たせているようだ。抑揚の効いた色使いは、総じて中世以前の涅槃図には見ることのない清新な気風をもたらしている。淡泊さと鮮烈さが同居するこのような彩色は、長崎を通じて流入した中国の作品に影響を受けたと考えられる。隠元隆琦(いんげんりゅうき・1592~1673)の来日、黄檗宗(おうばくしゅう)の伝来に象徴されるように、当代の中国仏教が普及すると、あわせて明末から清にかけての新しい様式の中国産仏画が日本にもたらされた。紙本の地(じ)の白さを活かした画面作り、濃密な陰影表現は、黄檗寺院に作例が伝わる福建地方の画家、陳賢(ちんけん)などの様式に近い。
色使いに加えて画面下方に集まった禽獣にも近世的表現を見ることができる。白象や獅子など定型的な図様がある一方、身近な哺乳類や鳥類、昆虫などは写実的に描かれている。とりわけ鳥類の描写(挿図4)は、写生図譜のそれを彷彿とさせる。円山応挙に学んだと言われる月僊であるが、写生を旨とする円山派の表現や彼らに受け継がれた粉本などを参考にしたのであろう。月僊自身も実物写生をよくしたと言われ、その経験が反映されているかも知れない。

挿図4
ユニークな悲しみの表情 月僊画の魅力
以上、本涅槃図の特徴を、前時代から継承した要素と新しい要素に分けて概観してきた。月僊は、旧来の形式に基づきながらも、近世の新しい様式を巧みに取り入れることで、個性的な涅槃図を生み出したと言えるだろう。最後に、月僊自身の個性が強く反映された箇所を見ておきたい。釈迦の死を悲しむ諸衆の姿は、前例を引用する旨は先に述べた。しかし個々の表情に着目すると、月僊らしい独特な表現を見つけることができる。それぞれ、赤く目を泣き腫らし、悲しみに暮れる様子を描いているが、不思議と悲痛な趣が無い。誇張された表情は大仰でどこか滑稽でさえある。とりわけ釈迦の上部に来集した菩薩衆の表情が笑いを誘う(挿図5)。感情を激しく発露する弟子や諸天と異なり、菩薩は威儀を失わず慈悲深い様子で描かれるのが通例であるが、ここでは人間味あふれる悲しみの表情を見ることができる。月僊は、独特の風貌を持つ仙人の絵が話題を呼び、全国的な人気を博した画家であった。どうやらその個性は、法要のために制作された仏画にも及んでいるらしい。視覚的興味を惹き付ける面白い表現は、本堂の内陣奥に本尊として掛けられる涅槃図を、より身近なものにしてくれるだろう。そのような本作の性格には、社会福祉事業を通じて、多くの人々に仏の恩徳を説いた僧侶月僊の姿が重なり合うようだ。

挿図5
参考文献
名古屋市博物館 編集・発行『企画展 尾張の仏教美術 涅槃図―描かれた釈迦入滅の情景―』1997年。
名古屋市教育委員会 編集・発行『名古屋市内寺院の仏画』(名古屋市文化財調査報告37)1998年。
滋賀県立琵琶湖文化館 編集・発行『釈迦の美術』2003年。
一宮市博物館 編集・発行『企画展 お釈迦さまのものがたり~涅槃図から読本・草双紙まで~』2009年。
赤澤英二『涅槃図の図像学―仏陀を囲む悲哀の聖と俗 千年の展開―』中央公論美術出版、2011年。
(横尾拓真)